|
|
TOP>有料老人ホーム検索>緊急対応 |
|
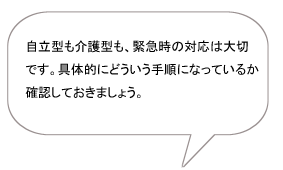 |
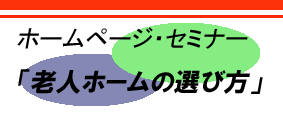 |
講師:山中由美
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、福祉住環境コーディネーター、NPO京都府認知症グループホーム協議会監事、など |
 |
もも編集室のセミナーから
重要なポイントをピックアップして
もも編集室の名物講師がわかりやすく解説! |
|
|
|
|
緊急対応
利用者の緊急事態や防災など、あらゆる面でチェックしておきたい
|
| |
緊急対応には、「利用者の体調急変時」と「火事や地震など災害時」があります。
いずれも有料老人ホームの場合、対応を指導されていますが、名目上でなくしっかりと手順をふまえて訓練されているかどうか確認しておきたいものです。
●利用者の急変時
これも自立型と介護型で対応が若干異なります。
介護型の場合、介護度や利用者の状態に応じて、居室にいる際にも昼夜を通して定期的に様子うかがいをするところが多いようです。中には、居室内にテレビカメラを設置し(本人や家族の了解の上)、ヘルパーステーションで随時確認している場合や、プライバシーの関係から赤外線で動きだけを察知するケース、またセンサーマットなどを利用し、利用者がベッドから離れようとした際にステーションに通報されるシステムなど、施設により取り組みはさまざまです。
特に気にかけていない施設もあります。
利用者や家族の希望にもよりますが、介護型でも上記のように非常に幅広い体制です。しかし共通していえることは、本人が自ら救援を希望した際に、しっかりと連絡できる体制があるか、迅速に対応しているか、その後の連絡はどうなっているか、などです。
有料老人ホームの場合も、「協力病院」は必ず設定せねばなりませんが、名前だけのところも多くあります。名前だけの大きな病院よりも近隣の親切丁寧な医師のほうが、安心できるケースもあります。協力病院との実質的な関係を確認しておきましょう。
自立型の場合は、利用者が元気で自立しているため介護型ほど常に管理されることはありません。自ら緊急連絡をできるシステムがあるかどうか、その後の対応はどうなっているか、は介護型と同様しっかり確認しておきたいもの。
また、自立型の場合も、生活リズムセンサー(居室にいるのに12時間以上水を流した気配がない・・・トイレ等利用していない)で、職員が確認する場合があります。年間数人が居室で倒れているところを見つけてもらい、事なきを得たという話もよく聞きますので、不安のある方はこのようなシステムも考慮しておきたいものです。
●防災の観点
有料老人ホームの場合は、緊急時(火災など)の防災訓練も課されています。年1回以上が原則ですが、自主的に毎月や半年に1回などしているところもあります。
過去、高齢者施設での火災で多くの人が亡くなった事故もあります。しっかりと防災訓練がなされているか、特に夜間は職員が極端に少なくなるので、体制は大丈夫か、など調べておきたいもの。
火災防止のために、居室では火器厳禁にしている場合もあります。最近では、喫煙も専用の喫煙ルームのみというところも増えています。
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|

